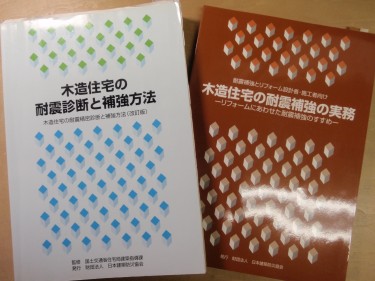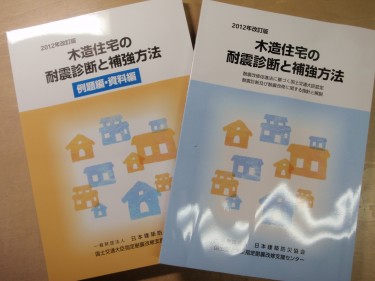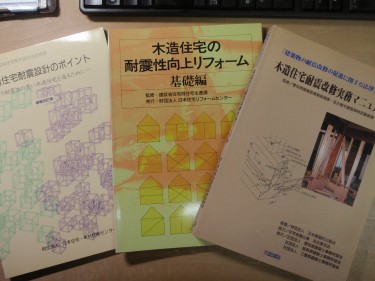平成17年11月に明らかとなった、
構造計算書偽装問題により建築士法が改正され
建築士は三年ごとに定期講習を受けなければならなくなりました。
早いもので前回の定期講習から既に3年が経ち、
今日は2度目の定期講習に行って来ました。
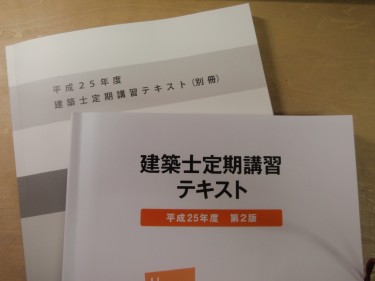
テキストは217ページ、ほぼ全ページを
5時間の講習時間でなぞり、ポイントを確認し、
最後の1時間で修了考査を行います。
修了考査はテキストを参照することが許されており、
60分で40問正誤の2択の問題です。
1問当り90秒は結構必死で取り組まなければなりませんでした。
45分でひと通り回答をして、
じっくりテキストを確認したい問いが2問ほどありましたので、
残り15分で見直しできました。

神奈川県で行われる今年度の定期講習は
おそらく今日が最後だと思います。
受講者は213人、3人掛けにギッシリで、
講習だけでも既に疲労感がありましが、
考査が終了した時点ではもうグッタリでした。